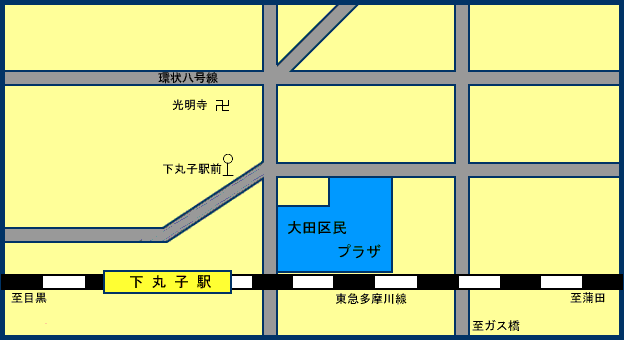|
はじめに
歴史は10年くらいで変わるときは急激に変わることを、歴史を研究していて実感します。例えば、65年前の今日12月8日は、日本がアメリカ、イギリスを相手に戦争を始めた日です。日本をとんでもない破局に導くわけです。そしてその10年前1931年は満州事変が起こった年ですが、その当時、日本が将来アメリカ、イギリスと戦争をすることを考えた人は、そんなに多くないと思います。さらにその10年前の1921年は、軍縮条約に調印した年です。そのときに、日本が後の15年にわたる戦争に突入することを考えた人はどれくらいいるでしょうか。このように、歴史は、変わるときには大きく変わります。これは、非常に恐ろしいことです。 |

|
|
本来、軍事とか戦争など考えなくていい世の中が一番いいのですが、改憲論が出てきて、軍事の問題を考えざるを得ない状況になっています。改憲論者は、日本の軍事力の現実と憲法が大きく乖離している。だから、現実に合わせて憲法を変えるべきだと主張します。しかし、軍事の現実は一体何か、ちゃんと示されたことはほとんどありません。その、よく判らない現実に憲法を合わせることは危険なことです。現在の日本の軍事力の現実と今後どうなるかについて、知っておかないとまずいことになります。
それから、そうはいっても北朝鮮が核実験をしたりして物騒じゃないか、日本も強力な軍事力を持つべきだとの議論があります。しかし、北朝鮮は戦争ができる国なのかどうか考えてみたい。そして、改憲論の問題点についても触れなければいけないし、また憲法9条はお題目に過ぎないのか、実際に私たちの生活をどう守ってきたのかについて、考えてみたいと思います。 |
|
Ⅰ 現代日本の軍事力の特徴
1 戦力としての自衛隊の世界的ランキング
日本の軍事費支出の世界のランキングは、1995年以来2~4位で、現在は4位くらいです。5位を下ることはまずありません。毎年5兆円を使っています。アメリカは、その10倍、50兆円で、世界の軍事費全体で100兆円だから、うち半分をアメリカが使っています。アメリカというのはとてつもない超軍事大国です。しかし日本も、5兆円も使っていますから、自慢できません。
日本の軍事力そのもので特徴的なのは、海上自衛隊です。湾岸戦争以降の15年間で、軍艦の総トン数を
1.5倍の44.6万トンにしています。船の数は変わらずに1隻ずつが大型化してきている。つまり遠くまで行けるように、船を大型化している。国民の知らないうちに既成事実が進んでいるのが実態です。これは米・ロ・中・英に次いでおり、日本は世界第5位の海軍国です。
陸上自衛隊は、14.7万人で、大きな兵力を持っている中国などもあるので兵力数は世界17位ですが、それでも英・仏・伊より上位にある。また航空自衛隊は12位前後ですが、英・伊・イスラエルよりも上位にある。どうしてそうなっているかというと、冷戦の終結でヨーロッパの国々は軍縮したのに、日本は軍縮しなかったので、日本が浮き上がってきたわけです。
|
|
2 日本の軍事力の<現実>――自衛隊の軍事力の2重のゆがみ
冷戦時代には、自衛隊は対ソ連の対潜水艦戦のための戦力として期待されており、その戦力が肥大化しています。これが1番目のゆがみです。例えば、対潜水艦戦能力が過剰になっています。100機近い対哨戒機P3Cは、態勢はそのままですが、今では追跡すべき潜水艦がいない状況になっています(冷戦時代には、日本近海にソ連だけで30~40隻あったのが、今はロシア、中国を合わせて10隻くらいしかない)。また対潜水艦戦護衛艦も過剰になっています。ヘリ3機を搭載した5000トンくらいのヘリ護衛艦は、本来3機も積むのは無理があり、世界でも珍しい艦種です。普通の海軍であればヘリ空母を持つところを憲法9条の制約で空母保有はできないため、護衛艦に分散して積む形をとっているのです。 |
|
そして、「はるな」型(4950トン)の“更新”として、13500トンの16DDH2隻の建造が承認されました。これはあくまでもヘリ搭載護衛艦の更新という形をとっていますが、イメージ図を見れば、形は空母です。このように、冷戦時代のゆがみがそのまま引き継がれています。 |

|
|
2番目のゆがみは、遠征能力の肥大化です。もともと自衛隊は専守防衛ということで、遠征能力は必要なかったのに、湾岸戦争以降、米軍の世界展開に対応して、遠征・情報収集能力が高められてきました。
遠征、情報収集能力の向上のため、イージス艦が導入されました。現在4隻就役中で、さらに2隻が建造中です。イージス艦は弾道ミサイル防衛の主役にもなります。長距離輸送・補給能力の向上という点では、「おおすみ」型輸送艦(8900トン)が3隻就役しています。これは上陸作戦に使うエアクッション艇(50トンの戦車も運べる)2隻を積んでおり、輸送艦というよりは、強襲揚陸艦です。これも、「あつみ」型輸送艦(1480トン)を“更新”した形をとっています。さらに、2004年度「ましゅう」型補給艦(13500トン)が就役し、テロ対特措法に基づいてインド洋で、アフガン戦争をやっているアメリカの艦船に補給活動をしています。
イージス、「おおすみ」、「ましゅう」、これらはすべてこの15年間につくられました。これらはすべて“更新”といっているが、大型化して、以前の護衛艦、輸送艦、補給艦とは全くの別物になっています。こうして自衛隊は冷戦時代のゆがみをそのまま引き継ぎながら、湾岸戦争以降、専守防衛とは関係ない遠征能力を異常に肥大化させています。二重にゆがんでいるといえます。改憲論者は二重のゆがみを前提に、こちらに合わせて原則を変える、正式に軍隊にしてシビリアン・コントロールをすればいいではないかというが、自衛隊の現状を見れば、どこにシビリアン・コントロールが効いているのだろうか? 現状でできていないことを、発言力が強まる軍隊になって、コントロールできるわけがありません。
この現実に合わせて憲法(原則)を変えようとしています。しかし、自衛隊に賛成という人も、専守防衛だから支持という人も多いわけで、それらの人も含め改憲について国民的合意が得られているわけではありません。 |
|
Ⅱ <米軍再編>と自衛隊
1 <米軍再編>とは何か
現在、<対テロ戦争>への対処のための米軍再編が進んでいます。冷戦後、もともと中東と朝鮮半島などの地域紛争への早期展開・長期展開に対応するためのアメリカの軍事力の再編成が行なわれましたそしてさらに“見えない”脅威への対応、<対テロ戦争>への対応力を強めようとしています。
|
|
米軍再編は、地域紛争だけでなく、対テロ戦争への対応でも、必然的に、同盟国軍の再編を含みます。先端的介入戦力としての米軍、補助的攻撃戦力としての同盟国軍(イギリスなどが担っている)と支援・補給部隊としての同盟国軍(日本など)です。従来、日本の自衛隊には補給・輸送が求められていましたが、今回の再編では補助的攻撃戦力としての役割が求められています。 |

|
|
2 自衛隊の役割の変化
イラク戦争段階では、自衛隊には支援・補給部隊としての位置づけがされているが、北朝鮮危機段階では、補助的攻撃戦力としての性格が強まります。すでに、弾道ミサイル防衛という形で始まっています。これは自衛隊を大きく変質させるものです。弾道ミサイル防衛(BMD)構想を突破口にして、この役割の変化を実現しようとしています。 |
|
3 自衛隊を大きく変質させる弾道ミサイル防衛(BMD)構想
「新・防衛計画の大綱」(2004年12月策定)の目玉としてBMD構想、これは、イージス艦のSM3とパトリオットPAC-3の2段構えで構成されています。敵の弾道ミサイルを、ミッドコース段階ではイージス艦のSM3で撃ち落し、ターミナル段階ではパトリオット地対空ミサイル(PAC-3)で撃ち落すというものです。この構想は、ミサイル防衛の効果については疑問視されていながら、新たな大軍拡の火種に結びつくし、また先制攻撃につながる危険な迎撃思想でもあります。そしてこの構想を「北朝鮮脅威論」が後押ししています。
BMD構想はもともとアメリカが開発したシステムで、ロシアなど遠距離からミサイルが飛んでくることを想定しています。その場合には、発射から着弾まで20~30分くらい判断のための時間がありますが、北朝鮮から日本だと判断の時間は10分足らずです。このシステムでは間に合わないことになります。したがって、使えるものかどうか、極めて怪しい。仮にすぐ意思決定ができるとしても、SM3で撃ち落せる確率は半分、PAC3で打ち落とせる確率は半分くらいです。とすると、撃ったミサイルの4分の1は落ちてくることになります。PAC3の射程距離は10キロメートルくらいしかないから、日本中針ねずみのようにPAC3を配備しないと駄目ということになりますが、予算上はそんなことはできない。そこで、この話しは敵が撃つ前にたたくという方向へ必ず傾斜していくことになります。北朝鮮がミサイル実験をしたときに、当時の防衛庁長官が「敵基地攻撃能力が必要だ」云々と発言しましたが、先制攻撃につながっていきます。
アメリカはすでに、弾道ミサイル防衛の前の段階、上昇していくミサイルをレーザー光線で撃ち落すという実験に成功しています。大きな飛行機にレーザー光線発射装置を積んで相手国の近くに巡回させておくもので、それだけで戦争の原因になります。ミサイル防衛は、結局そのもっと前、先制攻撃につながっていくと理解すべきです。これは、軍拡という面でも考え方の面でも、非常に危険です。 |
|
Ⅲ 北朝鮮の軍事力の実態
そうはいっても、北朝鮮は怖そうだし、金正日は何を考えているのかわからないという不安の声があります。しかし、結論から言うと、北朝鮮は通常戦力がほぼ無力化していて、戦争ができる状態ではありません。ピョンヤンでの軍事パレードの映像がよく流されますが、上空は写っていません。これは、航空機、武装ヘリコプターが飛んでいないということです。 |

|
|
地上軍は勇ましく行進していますが、写っているミサイルは1950年代の旧式な地対空ミサイルで、普通、博物館に入っているような代物です。写るのはそのレベルです。昭和20年の「陸軍始観兵式」と同じです。昭和19年までは戦車も飛行機も出てくるが、20年になると、出てくるのは歩兵と馬ばかりです。燃料不足のためです。北朝鮮の状況はこれとかなり似ています。北朝鮮の空軍パイロットの年間飛行時間は15~20時間で、自衛隊のパイロットの10分の1でしかない。明らかに燃料不足です。しかも作戦機は590機となっているが、アメリカ・韓国・航空自衛隊に対抗できる第4世代戦闘機(Mig-29)は20機しかない。ほとんど使えない状態です。これでは制空権の確保は無理で、しかも深刻な燃料不足で、地上軍100万人も動けません。さらに貨物船は圧倒的に不足していて補給力はない。これでは大規模作戦はできないし、ましてや渡洋作戦は不可能です。したがって、通常の戦争はできないということになります。
そこで、北朝鮮は核とミサイルにこだわることになります。通常戦力の無力化を補う政治的な手段が核とミサイルです。「核兵器保有」発言、核実験と弾道ミサイル実験を「核ミサイル保有」と錯覚させる報道がされていますが、大きな間違いです。核ミサイルがすぐにでも飛んでくるわけではありません。現在配備されているミサイルには、核弾頭が積まれているわけではありません。北朝鮮のミサイルの投射能力は700キロぐらいで、核の小型化は簡単ではない。また核を積めるミサイルの開発も簡単ではない。いずれいつかはできるでしょうが、少なくとも数年はかかります。危機感にとらわれてはいけない、冷静に対処できる一定の時間の余裕はあるといっていいと思います。 |
|
1 自衛隊と「自衛軍」はどう違うか?
自衛隊が自衛軍になれば、「交戦権」を保持するわけで、案文を見ても、戦争に参加するのは当たり前、海外派兵、海外での戦闘を前提にしています。すでに既成事実が作られています。それでは、イラク派兵のようなことがあるのかというと、それでは済みません。軍隊になれば、戦闘行動に参加することは、当たり前になるからです。一応、国際的には自衛隊は軍隊ではないということになっているので、補給とか復興・人道支援に限定されていました。ところが、軍隊であるということになれば、戦争に参加することは当たり前になる。ですから同じではない、やることは当然変わってきます。
またこの憲法草案には、「軍事裁判所」の設置も規定されています。軍法会議です。軍の内部の司法権を独自に持つということです。そして草案には何も書いてありませんが、軍事裁判所を設けるということは、「憲兵」の設置も不可避となります。憲兵は、軍事機密を守るという任務があるために、スパイの取締りということで、軍人だけでなく民間人も取り締まることになります。防諜機関、スパイ防止法も当然出来てくる。それからスパイを防止するということは、実はスパイ活動をするということでもあります。
スパイをしないとスパイ防止もできない、防諜機関を作るということは、諜報機関を作るということでもあります。決して、現状の追認ということだけではありません。
|
|
2 「自衛軍」が設置されると何が変わるのか
「戦力」の保持を明記することで、現在いろいろある歯止めがすべて取り払われます。また憲法による後ろ盾で「軍人」が登場することで、軍人募集は、堂々たるものになります。当然、大々的、組織的なものになります。学校や企業を巻き込んだ入隊勧誘や体験入隊に当然なります。高校卒業後大学に入学するまでの半年間はボランティア活動をやるべきだ、などとよくいわれますが、半年間というのは基礎軍事訓練にちょうどいい時間です。ボランティア活動が「基礎訓練6ヶ月」に利用されることも十分ありえます。プロフェッショナルな軍人には長期間にわたる訓練が必要ですが、軍隊では、それ以外の基礎訓練を受けただけで十分有効な人員が大量に必要です。車を運転できて、パソコンを使える今の若者は、結構使えるはずです。
|
|
1 戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認の3原則
私たちは9条を守るために運動しています。9条があるかないかは大きな違いです。特に、9条の第2項(戦力不保持・交戦権否認)を変えたいというのが、自民党の案です。戦力不保持、交戦権の否認が実に大きな足かせになっているということは、確かです。
|

|
|
2 戦力不保持規定の重み
「戦力」とは「自衛のための最低限度を超えるもの」とされ、警察予備隊、保安隊、自衛隊はいずれも「戦力」(軍隊)ではないとされてきました。そして、自衛隊の任務は「専守防衛」である、とされてきました。「戦力」でないことによる制約として、武器の質・量、使用法、製造・販売に一定の制約が生じています。「戦力」を肯定するということになると、これらすべての制約が解けてくる。武器輸出も可能になるし、軍艦の隻数など数量面での制約もなくなる。これまで恐る恐る既成事実を作ってきたが、その制約がなくなるということです。また核兵器、長距離ミサイル、長距離爆撃機、攻撃型空母などは保有できないとされてきました。ただし、「爆撃機」といわず「支援戦闘機」、「駆逐艦」といわず「護衛艦」というなどの言葉によるごまかしや、独特の兵器(ヘリ搭載護衛艦など)を生んできました。それでも9条の縛りがあって、何でも持てたわけではない。制約がなくなれば、どう呼ぼうと堂々と持てるようになるわけです。
「軍隊」でないことの制約として、隊員募集への制約もそうですが、海外派兵への制約があります。PKO、イラク派兵と、だんだん制約は緩んできましたが、「軍隊」でないという建前から、戦闘行動を伴う携行武器や任務に制限があります。そういう縛りがあった。それがなくなるということです。
|
|
自衛隊は憲法9条に拘束されています。9条を使って、さらにこれをコントロールすべきです。自衛隊が、例えばミサイル防衛構想で軍拡すると中国が軍拡する、するとインドが、そしてパキスタンが軍拡に走り、世界レベルでの軍拡につながる恐れがあります。それがさらに日本の軍拡を招くという悪循環に陥ります。中国を軍拡させないためには、日本は軍拡すべきではありません。日本と中国は、アジアでもっとも軍事費を使っている国です。ここがちゃんと話し合って、軍縮をしていかないと駄目だということです。私たちは、憲法9条を拠り所としてそれを要求していくことができるし、またしないといけない。そうしないと、いつまでたっても状況は変わらないし、中国を軍拡に走らせてしまうと世界的な軍拡になってしまう。場合によっては、極東での戦争ということも現実になるかもしれません。
私たちは9条を生かして、いかに世界的な平和を実現するかを考えていくべきです。世の中10年、20年で激変してしまいます。歴史は動くときには急激に動く。しかし、戦前と戦後は違います。戦前は、民意が政治に反映できないシステムでした。しかし戦後は軍事を民意でコントロールすることが可能です。
そのことを自覚して、憲法9条をいかに使っていくかが大切なことだと思います。 |
|
|
|
|
|
|
|
<質疑応答>
*質問:憲法9条2項の縛りがあるにも拘らず、なぜ戦後60年の間に世界有数の軍事力になってしまったのか。なぜシビリアン・コントロールが効いていないのか。なぜ、憲法9条体制は崩壊の危機に追い込まれているのか。山田先生の認識をお伺いしたい。
山田:安保条約の存在が大きいと思います。アメリカの要請にもとづいて、それが日本の軍事力のゆがみに現れています。米軍再編は、イコール自衛隊の再編強化であり、それが繰り返されてきました。安保条約が、日本の軍事力がここまで大きくなってきた一番大きな要因です。
*質問:軍事力の行使と警察権の行使の違いを先生はどのようにお考えですか。例えば、海上自衛隊と海上保安庁の違いは何ですか。
山田:警察権は隊員の護身が武器使用の基準です。例えば海上保安庁で、相手への威嚇という場合もありますが。軍事権は、護身もあるが相手を軍事力で制圧することに重きを置いています。国家の政策によって、先制攻撃もありえます。警察と軍隊では意味合いが違ってきます。警察権が他国に先制攻撃するということはありえません。
|
|
(文責:事務局・若林) |